プロフィール
- 弘前在住30代パパ&営業マン
- note & ブログ100記事チャレンジ中
- 朝活・夜活でコツコツ積み上げ
はじめに
夜ログは、その日感じたことや気づきを整理する記事です。
今日は「子どもにテレビやYouTubeを見せすぎるのは良くないのか?」というテーマ。
育児をしていると必ず出てくる話題ですし、SNSを見ても「スクリーンタイムは制限しないとダメ」という意見が多い。
でも、実際に子どもと過ごしていると「いや、動画から得ていることも多いんじゃないか?」と思う場面がたくさんあるんです。
今日のテーマ
子どもと動画との付き合い方について
本文
1. 「見せすぎ=悪」だけでは片づけられない
子育て本や専門家の話では「幼児の動画視聴は1日1時間以内」といった目安がよく紹介されています。
確かに、長時間ぼーっと動画を見続ければ、外で遊ぶ時間や親子の会話が減ってしまうリスクはあると思います。
ただ、現実の子育てはきれいごとだけでは回りません。
親だって家事や仕事で手が離せないときがあるし、どうしても子どもに動画を見てもらわないと回らない時間がある。
そんなとき「全部ダメ」と割り切るのは正直ムリです。
「助かるな」と思う気持ちと同時に「見せすぎかな」と葛藤する。これが多くの家庭の本音じゃないでしょうか。
2. 動画から学んでいることは想像以上に多い
実際、うちの子を見ていると動画から吸収していることは本当に多いなと感じます。
たとえば大好きなアンパンマン。
気がつくと歌を口ずさんだり、音楽に合わせて手を叩いたりしているんです。
最初はただ画面をじっと見ているだけだったのに、今では歌に反応して体を動かすようになった。
成長を感じる瞬間があって、「見せて良かったな」と思うこともあります。
さらに、YouTubeの教育チャンネルから数字やアルファベットを覚えたり、色の名前を言えるようになったり。
料理動画を見ていると、手を伸ばして混ぜるような動きを真似したり、こちらのやっている姿をじっと観察したり。
まだ言葉では表現しませんが、興味を持って関わろうとする姿が見えてきます。
僕自身も学生時代を振り返ると、テレビやネット動画から得た知識や言葉の影響は大きいです。
それが今の仕事や考え方につながっていると思うと、子どもにとっても「動画=ただの暇つぶし」ではなく「成長のきっかけ」になっているのではないかと思います。
3. 大事なのは「時間」より「内容」と「関わり方」
もちろん、好きなだけ見せればいいという話ではありません。
大事なのは「どんな動画を見るか」と「どう関わるか」だと思います。
刺激が強すぎたり、ただの娯楽で終わってしまう動画ばかりでは良くない。
でも、教育的な内容や音楽、自然や動物の映像などは、子どもの世界を広げるきっかけになります。
そしてもう一つは「親が一緒に関わること」。
一緒に見ながら「これ何色だね」と声をかけたり、「アンパンマンと同じ動きしてみようか」と一緒に体を動かしたり。
そんなふうにちょっと関わるだけで、受け身の視聴からコミュニケーションに変わっていきます。
わが家でもアンパンマンを見ながら一緒に歌って手を叩く時間は、親子の思い出として残っていくし、ただの動画視聴以上の意味があると感じます。
まとめ
- 「見せすぎ=悪」と言われるけど、実際の子育てでは動画に助けられる場面は多い
- 動画から歌や言葉を覚えたり、興味を広げたり、学びは想像以上に多い
- 大事なのは「時間」よりも「内容」と「親の関わり方」
読んでくれた方へ
ここまで読んでいただきありがとうございます。
子どもと動画の付き合い方って、家庭ごとに正解が違うと思います。
「うちも同じだな」と共感してもらえたり、「こうしてるよ」という工夫を思い出してもらえたら嬉しいです。
ぜひコメントや感想などで教えていただけると励みになります。
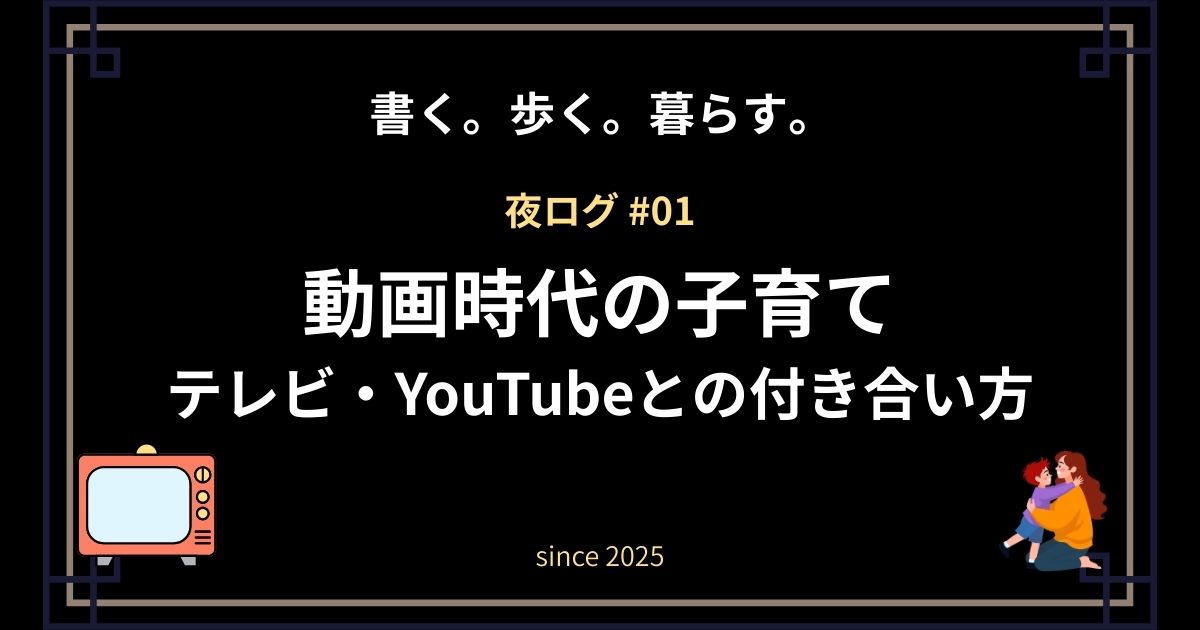
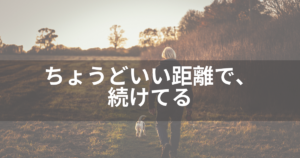

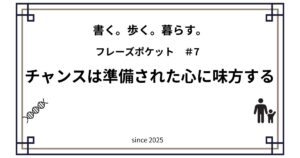
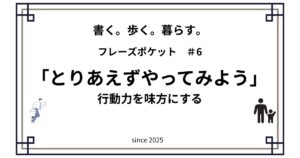
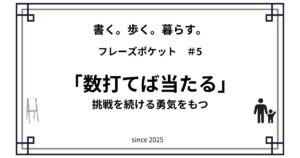
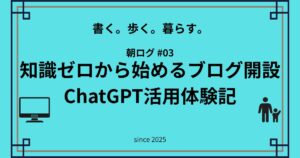
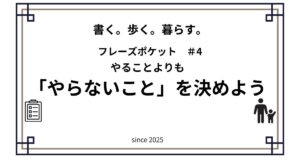
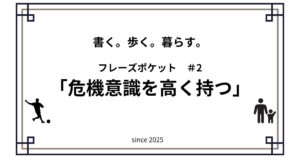
コメント